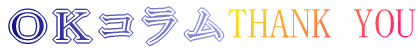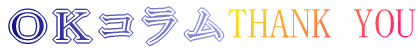| 地震はいつ来るの?(意味・歴史・地域・時期) |
|
|
古来から日本で頻繁に起こり、自然災害として大きな被害を
与えてきた地震ですが、地震が来る時期や地域は予測する事が
できないのでしょうか?過去の歴史を調べれば、地震が発生する
時期や地域をある程度予測できそうです。そこで早速、
地震の歴史から、地震の来る時期や地域について予測してみました。
地震とは?(意味)
地球表面を構成している岩盤(地殻)の内部で固く密集
している岩石同士が、断層と呼ばれる破壊面を境目にして
急激に動く事を言います。
※マグニチュードとは、地震のエネルギー量を示します。
| 死者数1000人を超える超巨大地震のみを記載します。 |
| 発生時期 |
地震名 |
発生地域 |
マグニチュード・死者数 |
| 紀元前4世紀〜紀元前3世紀 |
名称なし |
千葉〜東北部沿岸 |
M9の巨大地震・津波
死者不明
|
| 11年頃 |
名称なし |
高知県 |
M9の巨大地震
死者不明
|
| 4世紀〜5世紀頃 |
名称なし |
千葉〜東北部沿岸 |
M9の巨大地震・津波
死者不明
|
| 869年7月9日 |
貞観地震 |
東北地方沿岸部 |
M8.3〜8.6
地震に伴う津波による被害が甚大で約1000人が死亡
|
| 887年7月29日 |
名称なし |
新潟県西部 |
M6.5
地震に伴う津波による被害が甚大で約1000人が死亡
|
| 1096年12月11日 |
永長地震
(東海・東南海・南海地震) |
高知県〜静岡県にかけての沿岸部 |
M8〜8.5
地震と津波の被害で死者1万人以上
|
| 1293年5月20日 |
鎌倉大地震 |
神奈川県 |
M7.1
死者数約2万3千人
|
| 1361年7月26日 |
正平地震(康安地震・東海・東南海・南海連動型地震) |
高知県〜静岡県にかけての沿岸部 |
M8.4〜M8.5
死者数多数
|
| 1498年9月11日 |
明応地震
(東海・東南海・南海連動型地震) |
高知県〜静岡県にかけての沿岸部 |
M8.2〜M8.4
地震と津波の被害で死者3万〜4万人 |
| 1586年1月18日 |
天正地震 |
愛知・三重・岐阜・山梨・長野・滋賀県 |
M7.8〜8.1
死者数多数(1000人以上)
|
| 1596年9月5日 |
慶長伏見地震(慶長伏見大地震) |
京都・大阪 |
M7〜7.1
死者数1000人以上
|
| 1605年2月3日 |
慶長地震(東海・東南海・南海連動型地震) |
高知県〜静岡県にかけての沿岸部 |
M7.9〜8.0
死者数1万〜2万人
|
| 1611年9月27日 |
会津地震 |
福島県 |
M6.9
死者数約3,700人
|
| 1611年12月2日 |
慶長三陸地震 |
岩手県 |
M8.1
地震と津波の被害で死者2000〜5000人
|
| 1662年6月16日 |
寛文近江・若狭地震 |
福井・滋賀県・京都府 |
M7.3〜7.6
死者数約1000人
|
| 1666年2月1日 |
越後高田地震 |
新潟県 |
M 6.4
死者約1,400〜1,500人
|
| 1703年12月31日 |
元禄地震(元禄関東地震) |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
M8.1
死者約5,200人
|
| 1707年10月28日 |
宝永地震(東海・東南海・南海連動型地震) |
高知県〜静岡県にかけての沿岸部 |
M8.4〜M8.7
死者約2,800〜2万人
|
| 1751年5月21日 |
高田地震 |
新潟県 |
M7〜7.4
死者約1,541人
|
| 1766年3月8日 |
津軽地震 |
青森県 |
M6.9
死者約1,500人
|
| 1771年4月24日 |
八重山地震 |
沖縄県の周辺の島々(石垣島等) |
M7.4〜8.0
死者約1万2千人
この時の津波の高さは85mだったと言われています。(日本記録)
|
| 1792年5月21日 |
島原大変肥後迷惑 |
長崎県 |
M6.4
死者約1万5千人
|
| 1828年12月18日 |
三条地震 |
新潟県 |
M6.9
死者約1681人
|
| 1847年5月8日 |
善光寺地震 |
長野県 |
M7.4
死者約1万〜1万3,000人
|
| 1854年7月9日 |
伊賀上野地震 |
三重県 |
M7.3
死者約1,800人
|
| 1854年12月23日 |
安政東海地震(東海・東南海地震) |
三重県〜静岡県にかけての沿岸部 |
M8.4
死者約2千〜3千人
|
| 1854年12月24日 |
安政南海地震(南海地震) |
高知県〜三重県にかけての沿岸部 |
M8.4
死者約1千〜3千人
|
| 1855年11月1日 |
安政江戸地震 |
東京都・千葉県 |
M7〜7.1
死者約4700〜1万千人
|
| 1891年10月28日 |
濃尾地震 |
岐阜県・愛知県 |
M8.0
死者約7,273人
|
| 1896年6月15日 |
明治三陸地震 |
東北地方沿岸部 |
M8.2〜8.5
津波・地震により死者約2万1,959人
|
| 1923年9月1日 |
関東地震(関東大震災) |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
M7.9
死者約10万5,385人
日本災害史上最悪
|
| 1933年3月3日 |
昭和三陸地震 |
東北地方沿岸部 |
M8.1〜8.4
死者約3,064人
|
| 1943年9月10日 |
鳥取地震 |
鳥取県 |
M7.2
死者約1,083人
|
| 1944年12月7日 |
東南海地震 |
三重県〜静岡県にかけての沿岸部 |
M8.2
死者約1,223人
|
| 1945年1月13日 |
三河地震 |
愛知県東部 |
M6.8
死者約2,306人
|
| 1946年12月21日 |
南海地震 |
和歌山県〜高知県にかけての沿岸部 |
M8.2
死者約1,443人
|
| 1948年6月28日 |
福井地震 |
福井県 |
M7.1
死者約3,769人
|
| 1995年1月7日 |
兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災) |
兵庫県 |
M7.3
死者6,437人
|
| 2011年3月11日 |
東北地方太平洋沖地震(東日本大震災) |
東北地方(福島県・宮城県・岩手県沿岸) |
M9.0
死者約1万9千人
|
このように過去のデータを調べてみても、次にいつ・どこで地震が発生するか?はわかりませんが
歴史から見て言える事は、東海・東南海・南海連動型地震、関東(東京)の直下型地震、
東北地方太平洋沖地震は将来、必ず発生するという事です。それは、過去の歴史が
証明しています。過去、地震があった場所に住んでいるなら、いつ地震が来てもいいように
地震に対する備えをしておく事が大事です。また、過去の津波で85mという超巨大津波
が発生したという記録もありますので、もし、津波警報が発令されたらすぐ逃げるようにして下さい。 |
|
|
関連コラム:生活中の身近な疑問を調べてみた
日本はなぜ地震が多いの?(地震の原因・種類・活断層)
|
| mixiチェック
|
| 身近な豆知識が満載-OKコラムトップへ戻る |
|