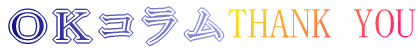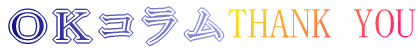| 招き猫(まねきねこ)の由来・歴史は? |
|
|
右手を上げた招き猫は、お金・福を招き、左手を上げた
招き猫は人・客を招くという意味があるという話は
招き猫の効果・意味というコラムで述べてきましたが、
招き猫の歴史・由来はどうなっているのでしょうか?
早速、招き猫の歴史・由来を調べてみました。
招き猫の歴史・由来
招き猫の由来には以下の説があります。
①今戸焼説
江戸時代末期、界隈に住んでいた老婆が貧しさゆえに愛猫を
手放したが、夢枕にその猫が現れ、「自分の姿を人形にしたら福徳を授かる」
と言ったので、その猫の姿の人形を今戸焼の焼き物にして
浅草神社(三社様)鳥居横で売ったところ、たちまち評判になったという。
※今戸焼とは・・・東京の今戸や橋場とその周辺(浅草の東北)で
焼かれていた素焼の陶磁器の事を言います。
※浅草神社とは・・・東京都台東区浅草の浅草寺の境内にある神社。
浅草寺の草創に関わった土師真中知(はじのまなかち)、
檜前浜成(ひのくまはまなり)・武成(たけなり)を主祭神としています。
②豪徳寺説
江戸時代に彦根藩第二代藩主・井伊直孝が鷹狩りの帰りに
豪徳寺の前を通りかかった際にこの寺の和尚の飼い猫が門前で
手招きするような仕草をしていたため寺に立ち寄り休憩しました。
すると雷雨が降りはじめました。
雨に降られずにすんだことを喜んだ直孝は、後日荒れていた豪徳寺を
建て直すために多額の寄進をし、豪徳寺は盛り返しました。
その後、境内に招猫堂が建てられ、猫が片手を挙げている姿を
かたどった招福猫児(まねぎねこ)が作られるようになったのです。
※豪徳寺は東京都世田谷区にあるお寺です。
※井伊直孝(1590-1659)とは・・・
江戸時代前期の譜代大名。井伊直政の次男です。
大坂城の山里郭に篭っていた淀殿・豊臣秀頼母子を包囲し
発砲して自害に追い込むという大任を遂げ、その勇猛さは
「井伊の赤牛」と恐れられました。
③自性院説:その1
江古田・沼袋原の戦いで、劣勢に立たされ道に迷った太田道灌
の前に猫が現れて手招きをし、自性院に案内しました。
これをきっかけに盛り返すことに成功した太田道灌は、この猫の
地蔵尊を奉納したことから、猫地蔵を経由して招き猫が成立しました。
※江古田・沼袋原の戦いとは・・・
室町時代後期の1477年5月25日に武蔵国江古田・沼袋原
(現在の東京都中野区江古田・沼袋付近)で太田道灌と豊島泰経
との間で行われた合戦の事を言います。
※太田道灌(1432-1486)とは・・・
武蔵守護代、扇谷上杉家の家宰です。
江戸城を築城した武将として有名です。
※自性院は東京都新宿区にあるお寺です。
③自性院説:その2
江戸時代中期に、豪商が子供を亡くし、その冥福を祈るために
猫地蔵を自性院に奉納したことが起源であるとするものがあります。
このように招き猫(まねきねこ)の発祥の地として名を上げる所は
他にも存在し、明確な起源はわかっていないのが現状です。
招き猫(まねきねこ)は幸運・人を招くと言われているので、
色々なお寺が「発祥の地である」と言い始めたのではないか?
と考えられます。
現代の招き猫(まねきねこ)の生産地・豆知識
現在、日本一の招き猫の生産地は
愛知県常滑市となっています。(愛知県瀬戸市、
群馬県高崎市も生産地として有名です。)
また、毎年、9月29日[くる(9)ふ(2)く(9)]は
日本招猫倶楽部が制定し日本記念日協会が認定した
「招き猫の日」となっています。
日付の語呂合わせからして、9月29日は
幸運が舞い降りてきそうですね!! |
|
|
関連コラム:生活中の身近な疑問を調べてみた
「だるま(ダルマさん)」って誰?・なぜ赤いの?・目がないの?
招き猫(まねきねこ)ってどんな効果があるの?(意味は?)
|
| mixiチェック
|
| 身近な豆知識が満載-OKコラムトップへ戻る |
|