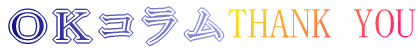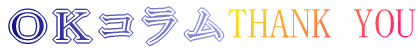カレンダーをふと眺めてみると大安や仏滅等の文字が目につきますが、
あれは、何を意味しているのでしょうか?歴史と一緒にまとめてみました。
六曜(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口)の歴史
六曜は中国で星の位置を区別する為につけられたものだと言われています。
1ヶ月(30日)を5等分して6日を1周期として用いていました。
西暦200年頃(三国時代)、諸葛 亮が発案したという説や
唐の李淳風が発案したという説がありますが、真偽はわかってません。
日本では、14世紀の鎌倉時代末期から室町時代にかけて伝えられ、
第二次世界大戦後、カレンダーに六曜が記載されるようになってから
爆発的に広まりました。
六曜の意味について
先勝(せんしょう・せんかち・さきがち・さきかち)
「先んずれば即ち勝つ」の意味。かつては「速喜」「即吉」と書かれていました。
万事に急ぐことが良いとされています。
友引(ともびき・ゆういん)
「凶事に友を引く」という意味です。つまり、この日に葬式を行うと
友達が冥土に引き寄せられる(=死ぬ)という事を意味しています。
友引の日は火葬場が休みになるのが基本です。
かつては、「勝負なき日と知るべし」といわれ、勝負事で何事も引分けになる日、
つまり「共引」とされており、現在のような意味はありませんでしたが、
中国の陰陽道で「ある日ある方向で事を行うと災いが友に及ぶ」という「友引日」
と混同してしまった為、現在の意味になってしまいました。
先負(せんぶ・せんぷ・せんまけ・さきまけ)
「先んずれば即ち負ける」の意味です。また、「午前中は凶、午後は吉」とも言います。
急がずゆっくりと物後を進めることが良いとされ、
勝負事や急用は避けるべきとされています。
かつては、「小吉」「周吉」と書かれ吉日とされていました。
仏滅(ぶつめつ)
「仏(ほとけ)も滅するような大凶日」を意味します。
「何事も遠慮する日、病めば長引く、仏事はよろしい」とも言われています。
この日は仏様も滅する最も凶な日である為、結婚式等の
お祝い事は避けられる傾向にあります。
かつては、「空亡」「虚亡」と言っていましたが、これを全てが虚しいと解釈して
「物滅」と呼ぶようになり、これに近年になって「佛(仏)」の字が当てられました。
仏様=仏教の開祖であるお釈迦様を指します。
大安(たいあん・だいあん)
「大いに安し」の意味です。何事においても吉、成功しないことはない日とされ、
特に婚礼は大安の日に行われることが多です。
また、内閣組閣も大安の日を選んで行われています。
かつては、「泰安」と書かれており、
本来はこの日に何も行うべきではないとする説もあります。
赤口(しゃっこう・しゃっく・じゃっく・じゃっこう・せきぐち)
「万事に用いない悪日、ただし法事、正午だけは良い」とも言われています。
午の刻(午前11時ごろから午後1時ごろまで)のみ吉で、
それ以外は凶とされています。 |